【新刊サンプル】ゼロ・アウト
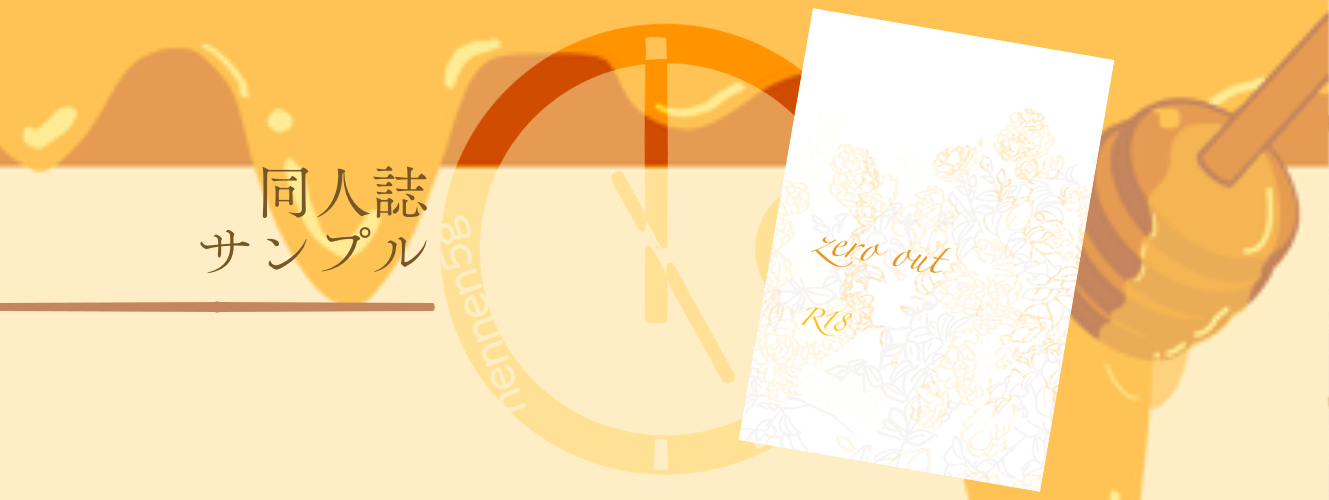
1 ずるいひと
ずっと会いたかった、ずっと会いたかったと言いたかった、でもそれを告げる機会はない、焦がれる相手。
日本中を熱狂させ、その最中にぷつりと消息を絶った、憧れのひと。
それが、九条の姿を借りて、十何年ぶりに、ミツの前に現れた。
開幕の瞬間、ミツが目を見開いて、声もなくつぶやく。
ゼロ。
夢中だった。目を輝かせて、あるいは涙をためて、ミツの大きな瞳は、九条の一挙手一投足も見逃すまいと、全身でその光を向いていた。
影の方にいる自分の体は、きっと、忘れてしまっているだろう。
隣でその目の輝きを見ている、出会って三年目の恋人のことも。
舞台ゼロの開幕は圧巻だった。八乙女と十さんのデュエットは、どこからいつ声を出しているのか疑いたくなるほど苛烈で、駆け上がるように鮮烈で、ゼロを語る舞台を飾るのにふさわしい。二体の長身がダイナミックに交錯するバク転の振り付けに、舞台を見ているというのに、観客席からわあっと歓声すら上がった。
一身にスポットライトを浴びて立つ三人。TRIGGERでなくては担えない舞台の重圧が、そのまま客席を快感の渦に引き摺り込んでいく。
暗転は一瞬。
「……そこで見ていて」
舞台上で、二人の男に背を向けて、九条が、いや、ゼロが言う。
ゼロをとりまく二人──十さんはかすかにほほえみ、八乙女は興奮したように、行っておいでとゼロに告げた。桜春樹と九条鷹匡をなぞって、代弁する、その葛藤が微塵も匂わない、美しい立ち姿。まだ生きている人の、あるいは最近亡くなったばかりの人の足跡を慎重に踏んで森の奥に分け入っているのに、かけらも迷いやためらいがない。
……自分が任せられたあの大仕事を思って唇を舐めた。あの役の足跡を俺が踏む時も、八乙女や、……千葉志津雄の足跡を崩さず、だけどもっと向こうへ行けるのか……少し、行きたい。二階堂大和が、あんなふうに、そこに。慣れなかった、誰かのための一生懸命を、自分のための一生懸命にして。
ゼロが、ブラックオアホワイトの舞台に上がる。隣りの男が息を飲んだ。
一度しかない自分の人生を、面白くできるのは自分だけだと笑っていた。俺が一生懸命になって、本気で悔し泣きするところも見たいと言った男。今日は、ゼロにさよならを言いたいと言っていた。
それなのに、告げるはずだった別れの準備を、もう思い出せないみたいに。ミツは両拳を握って、五歳の子どもがするような無邪気さで、額まで赤くして、舞台のゼロへ念じていた。
がんばれ。がんばれゼロ。ゼロならできる。オレはゼロが大好きだ。
思わず微笑みそうになる。
見ていれば、わかる。ミツが何を考えているかなんて。
ゼロが息を吸った。曲が始まると、ふっくらと火照ったミツの頬には、大きな雫が伝い始める。
何度も見たと言っていた、ゼロがブラックオアホワイトを制したときの曲。俺も何度も聴いた。ミツと車で出かけるたびにこの曲が流れるせいで、曲も、この曲を聴き終えたミツがうっとりと話し始めるまでの数秒の間も、穏やかなのに泣き出しそうな声音も、覚えてしまった。
ミツの小さな唇がまた動く。
「やっぱ」。
「いいなあ……」。
「ゼロ」。
チクリとどこかが痛んだのに、役者の二階堂大和でも、あいつらの同僚の二階堂大和でもない俺が、俺の中のどこで苦しんだのかわかる前に、舞台はエンディングに差し掛かっていた。
ゼロがいなくなった舞台で、九条が不在のゼロに慟哭し、桜さんがゼロの詞を眺める。
桜春樹の遺作。ちらりと見たナギの表情は、暗がりに見えなかった。
ミツが酷く泣いて、すすり泣きを押し隠すこともできないでいるのを、薄ら笑いを浮かべて聴く。これ、このあとCMにでも使われんじゃねえの、TRIGGERの舞台にIDOLiSH7が出しゃばったら、昔は客とったとか揉めたけど、今回は貢献できたことになんのかな、それともまたボールペン折られんのかな……なんて冗談みたいに思っていたら、そのIDOLiSH7のセンターが、舞台の上に立っていた。
驚きに集中を欠いたのも束の間、気づけば煽られ、歌い。劇場中が、リクの誘導に合わせて、九条へ歌声を向けた。
劇場が一体になる感覚は、舞台というよりライブのようで、煌びやかな舞台上で手をかざす九条と陸は、ゼロそのものにしか見えなかった。
wow、と九条に声を重ねる。ゼロへの鎮魂歌みたいな荘厳な歌。
でも、体を敗北感が満たした。
隣で泣きながら声を張る、あんたに憧れてアイドルになった俺の恋人は、俺の歌声も、IDOLiSH7の和泉三月だってことも、忘れちまったみたいに見える。
あんたが俺から、俺たちから、こいつを奪っていったみたいに……。
大泣きしていたミツは、最後には笑っていた。大きな口を開けて歌って。
告げるはずだった別れを再会に変えた、劇場を満たすコール&レスポンス。劇場のアイドル十六人を、きっとそこに一人のアイドル候補の女の子も巻き込んだ合唱の最後、ミツが笑顔を浮かべていたことに、今度はハッキリと、胸がいたんだ。
笑っていて欲しかった、ミツの笑顔に何度も安堵や勇気を貰ってきた、それなのに。
なぜか、今は、笑わないで欲しかった。割れんばかりに拍手しながら、舞台にとびきりの泣き笑いを向ける恋人の隣で。手のひらの痛みすら遠い。
ミツが大好きな唯一のもの。俺よりも先に出会って、俺よりも先にいなくなったものが、完璧な、それ以上の形で、ミツの前に現れてしまった。
「はは」
小さく、笑い声が漏れる。
「敵わねえ」
隣のソウが、そうですよね、TRIGGERほんとに最高、と興奮気味に相槌を打つのを、微笑んで受け流して、拍手を続ける。
去ったやつには敵わない。俺はこれから、一生あんたに嫉妬し続けんのかな。
ゼロに、なんの欠点もないことは、既に調べた。どんなに凄いやつが、俺の前にミツの内側に足跡を残したのか、その足跡にどうにか後ろめたいことは見つからないか。
結果は惨敗。ゼロにはなんのスキャンダルもなかったと、俺はもう知っている。
隣りのミツが泣き叫んだ。
「ゼロ……!」
ゼロ。
もう、ミツの前に、現れないでくれよ──。
*



