【新刊サンプル】ゼロ・アウト
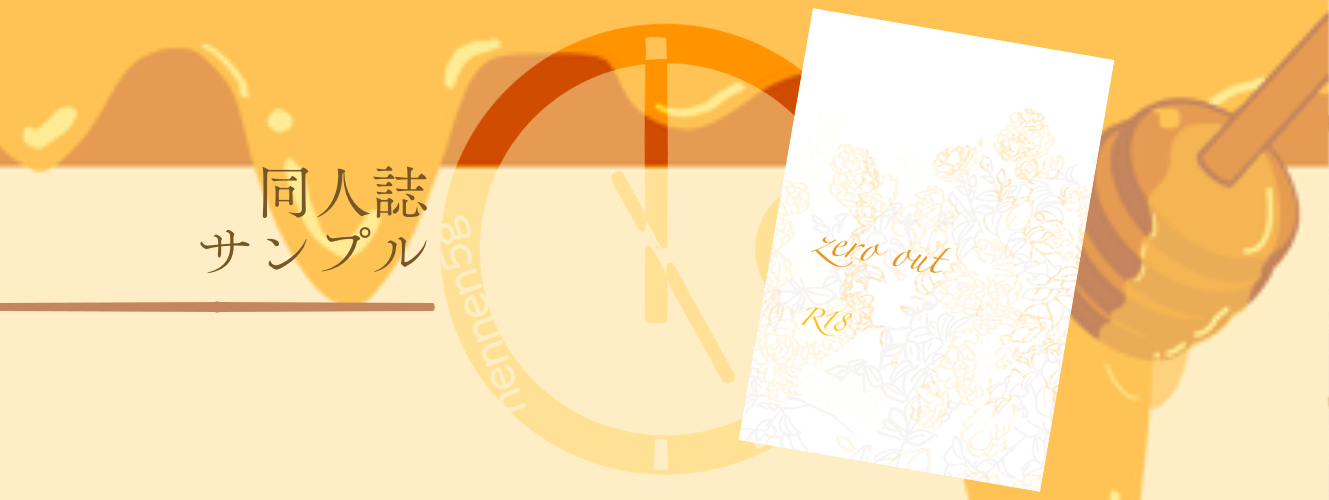
乾杯は何度も、たぶん二桁はゆうに重ねて、くすぐったそうなTRIGGERも、誇らしそうに満足気にそれを見るRe:valeも、既に俺たちの寮を後にした。
公演が無事に終わったTRIGGERを、何度も劇場に足を運んだ陸やミツが招いて、先輩も便乗した打ち上げ。
俺はその間、何度でも泣き出すミツのそばに居た。
「うう、ゼロ……ゼロぉ」
「はいはい、九条はもう帰ったって」
黒とオレンジの、オーバーサイズのパーカーの袖は、もうぐっしょりと濡れている。アイドルらしからぬ涙や鼻水が、ミツの顔中に光っていた。
「だって」
ひくっ、としゃくり上げるテンポも、今日だけで何度も聞いた。酔いだけではない高揚に、ミツが身を任せているのがわかる。
「あんたと同じところに来たよ、あんたのことが前よりわかるよって……思ってたんだけどさ。やっぱ分かんなくて、でもやっぱりゼロってすごくて……。オレ、あんなふうに、一緒に、ゼロと歌えるなんて……」
またミツが言葉に詰まって泣き出す。
「三月、お水いる?」
「あっばか、リクは離れてなさい」
「りく〜! おまえ……おまえ最高だよお、陸ー!」
「あはは! 三月ー!」
舞台ゼロを賞賛する塊となったミツが、舞台ゼロの影の立役者であるリクを抱き締め、もはや締め上げ。
青くなったイチがリクを剥がして、リクははしゃいで笑ったあと、少しだけ寂しそうにする……この光景も何度も見た。
九条は打ち上げの間、リクとは離れた席で、タマやミツやRe:valeに構われていた。
あの舞台のあとで、みんないる前でリクと話せなかったんだろう。
九条の戸惑いや、後悔ではないのにどこか気が咎める心地はよくわかった。いまさら気恥ずかしい。
相手がそばにいるだけで、なにかわるいことをしているような、でもとてつもなくいいことが起きていて、だから逃げたい気持ちになる。長く決別した家族との和解なんて、そんなものだ。
居心地がいいことが、かえってすわりが悪い。
ミツは抱きしめる相手を失い、うう、とか、ああ、とかまた泣いて、手にしたハイボールをひといきに煽った。
テーブルで、たん、と小気味良い音がしたと思うと、顔の横で、ぶんとグラスが風を切る。
「舞台最高ー! 生歌最高ー! TRIGGER最高ー! ゼロ、最高ー!!」
空になったグラスを振り上げてミツが叫ぶたび、グラスから氷ががらがらと落ち、床を濡らした。マジで酔ってんな、と目を眇めつつ、眼鏡を押し上げて、氷を拾う。
いつの間にか、この掛け声に喜んで応じる奴ら──ナギとソウの姿が消えていた。ひょっとしたら、どこかで話し込んでいるのかもしれない。リビングを見渡せば、タマはリクとイチに構ってやっていた。
掛け声に応じるものがいなくても、ミツの独白は続く。
「さよならも、っ、もしあんたがつらいことに気づけてなかったらごめんなも、大好きだよも……いっぱい、何度も、準備してたんだ、言いたくて」
あちこちに散らばった言葉をかき集めるような、不格好でとめどないミツの吐露。時折しゃくりあげながら続く言葉を、うなずいて聞く。
「でも全部っ……、あんな……うう、ゼロにまた会わせてもらえるなんて、ぜろのらいぶにまたいけるとか! ぜろぉ、大好き、愛してる! ぜろ……!」
呂律の回らない舌が、俺じゃない男への愛をさけんだ。
「……はいはい、聞いてる聞いてる。ゼロにもきっと届いてるよ」
「ほんとに? とどいてるかな」
「おまえさんだって、ファンの子がどこでお前さんを好きだっつってても、聞こえるぜーって言うでしょうが」
いつまでも夢見心地なミツに、ちょっとだけ現実らしいことを突きつけてみると、大きな目がぱちんと瞬いた。ゼロファンの和泉三月の背中で眠っていた、アイドルの和泉三月が、ちらりと視線をさまよわせる。
「……気づけるように、ひっく、したいと。おもっ……」
肩を上下させてしゃっくりをこらえてから、ぱちんと何かがはじけたように、ミツは動きをとめた。
「……寝たか? おーい。ミツ……」
ミツの目の前で手を振っても、反応がない。両肩を掴んでみても、ミツはぼうっと虚空を見ていた。
飲みすぎたか、電池切れか……。いつも朝までギンギンなやつが、こんな酔い方は珍しい。
心配そうにこちらを見るイチへ、明るげな声を張る。
「イチ、リクたち寝かしてやって。明日も仕事だろ」
「兄さんは……」
「飲みすぎたんだろ。はしゃぎ疲れもありそうだし、面倒見とくよ。飲ました大人の責任だわ。あとは、最高の舞台を作った和泉プロデューサーとリクのな」
「からかわないでください。七瀬さん、行きますよ」
「えー。もうちょっといようよ」
「明日早いんですから。また九条さんに怒られたいんですか」
「天にぃ怒るかな?」
「怒りませんよ、あなたがきちんと仕事をしていればね。ということで、寝ましょう」
「はーい。大和さん、おやすみなさい」
「おー、おやすみ」
イチもいよいよ、子供の扱いに長けた保母のようになり始めたな、と思うとおかしい。
幼いころ、おばけが来るかもと怯えて眠れないイチに、ミツはくまさんがやっつけてくれるから大丈夫だなんて言って寝かしつけていたらしい。安心させて寝かせるイチのやり方は、昔のミツに倣っているのかもしれない。
飲ました大人、と言ってから、そういえば、今日は飲みすぎる前にソウの姿が消えていた、と思い出す。
「タマはちょっとソウ覗いてから寝るか?」
「ん……いい。たぶんナギっちと話してっし。俺いないほーが、そーちゃんも、話しやすいだろ」
「そうか? あいつはお前さんに好きなもんの話する時が、一番ギラギラしてるけどな」
「俺はいいー」
もの思いしたような目付きをちらりと見せてから、タマは歌うように話題をかわし、背中を向ける。
ありゃ嘘だな、ソウとなんかあっただろ、タマがソウに隠し事してる感じか?
「反抗期だもんな、恥ずかしいこともあるか」
「恥ずかしくねーし! ヤマさんおっさんくせーぞ」
「いやー、うんうん、若いねえ」
「もー寝る!」
適当にはやしてつついても、タマは本音を見せずにリビングを後にした。うさんくさい大人を責めるイチの視線が、去り際に突き刺さる。
いや、今のはカマ掛けただけなんだって、メンバーのごたごたはお前さんも避けたいでしょうが……。
イチがリクを伴って消えるのを見送った頃、ミツが小さく何か言った。
「うん?」
聞き返すと、大きな目がくりんと上向き、俺を捉える。
「……大和さんは?」
「俺? が何?」
「大和さんも聞こえてる?」
「何……ああ、ファンの声な。まあ、そうかな……」
「ふふ、アイドルじゃん」
「そうだよ。お前さんとアイドルやってます」
「オレと……」
「ミツと。IDOLiSH7。やってるだろ?」
「きみとぉ、あいどりっしゅないと?」
「そうそう」
崩れた意識を取り戻すように、ミツが冠番組のお決まりの掛け声をつぶやく。
マジで酔ってんな。何度目かしれないため息をに呆れの言葉を混ぜると、自分の口から、やたらぶすくれた声が出た。俺も酔っているらしい。
この頃は、仕事がやたらに忙しくて、ドラマや冠番組の撮影以外で、ミツと顔を合わせることがなかった。忙しさはミツも同じで、寝るためだけに寮に戻ってきては、それでも何か食いものを冷蔵庫に突っ込んで姿を消す。
ミツの忙しさを助けてやれればと、俺が料理当番を代わったり、出前を頼んだりもしていたが、会話をする時間もなく、当然、抱き合ったり、キスしたりする間もなかった。
メンバー全員で舞台を見に行った後も、その忙しさを縫ってまた舞台を見に行ったようだから、じっくり過ごせたのは、今日の宴会が久しぶりだった。その間も、ミツはゼロに夢中だったわけで。
血色のいい唇が、目の前で、またむにゃむにゃとゼロのことを呟いている。
……仕方ないってわかってるけど……。
ごまかすように、ため息をもう一度ついた。嫉妬やら欲求不満やら、いろいろなものが溜まっている。
「寝るか。ミツ、リクのくれた水飲みな」
「うに?」
「言ってねえよ。水飲みな」
「おー……」
きょとんとしたミツに水を持たせ、宴会のあとを見渡す。
切り崩されてすっかり形を失ったケーキの塔は、ミツが作ったものだ。この宴会で九条とリクにまた歌わせた、あの曲イメージのケーキなんだという。
SNSにナギが投稿した画像がバズっていた。明日の朝のワイドショーで、司会がミツのゼロファンぶりとデザート作りスキルをいじるための台本を、今テレビ局の誰かが書いているだろう。
俺たちの日常は、とめどない。走って前に進むしかない。そんな、追い立てられるように連なって過ぎる時間のなかでも、ミツはミツの欲しいものにまっすぐ、ひた走っている。
ゼロ見たら、なんか作りたくなって、じっとしてらんなくて、と、ミツが紙に一生懸命デザインを描くのを、俺の知らないミツを見る目で見てしまった。
なんだ。俺いらねえじゃん。こいつ、ひとりで、自分の欲しいもん掴んで、でかい感情も自分で処理して、楽しそうで。
俺が、がんばりすぎるこいつの息をぬいてやりたいとか、なにか与えてやりたいって思ってたのも、なんか、アホくさいな。
……つーか、構えよ。付き合ってんじゃん。そんなことしてる暇あるなら……。
酔った頭は、ミツのケーキの残骸を、自分のあわい承認欲求の成れの果てのように見せつけた。本当はそんなこと思っていない、と自分に言い聞かせて、唇を噛む。
水を飲み干したミツが立ち上がり、キッチンへ向かった。
背中を見つめて、囁く。
「ここで言ってる声は、聞こえてないかもな」
ミツが水道をひねって、コップに水を満たす音に、声がかき消された。
「好きだって。俺もファンだって……」
当然、返事はない。リビングを出ようと立ち上がると、あれ、とミツが不思議そうに尋ねた。少し酔いがさめたのか、はっきりした声。
「部屋戻んの? まだ酔ってねーじゃん、おっさん」
「ここにいたって意味ねーし。さっさと退散しますわ、役立たずは」
「何の話だよ?」
「べっつにー。おやすみ」
とげとげしく言ってから、意地悪かったかな、と少しだけ後悔して、ついさっき反抗期扱いした、五つ下の長身の高校生の頭を撫でたくなる。
ミツが、たぶん唇をとがらせて俺を見ているとわかるのに、そうじゃない気もした。振り向いて、本当に俺を見ていなかったら……。
いつまでもゼロにとらわれたまま帰ってこない恋人に、素直に甘えてなんかやるもんか。
リビングの入口を抜けるとき、壁に貼られた日程表が目に入る。メンバーたちのスケジュールを記した七人分の枠の、上から二番目と、三番目には、文字が少ない。
明日は俺が夕方からで、ミツが朝だけ。……そんな日は、少しでも一緒にいようとしていたのに。今日のミツは気づきもしない。
リビングを去って、部屋のドアを閉めても、足音はせず。
ミツは追ってこなかった。




