方舟Ⅰ _暴かれて終わったオレたちの関係について
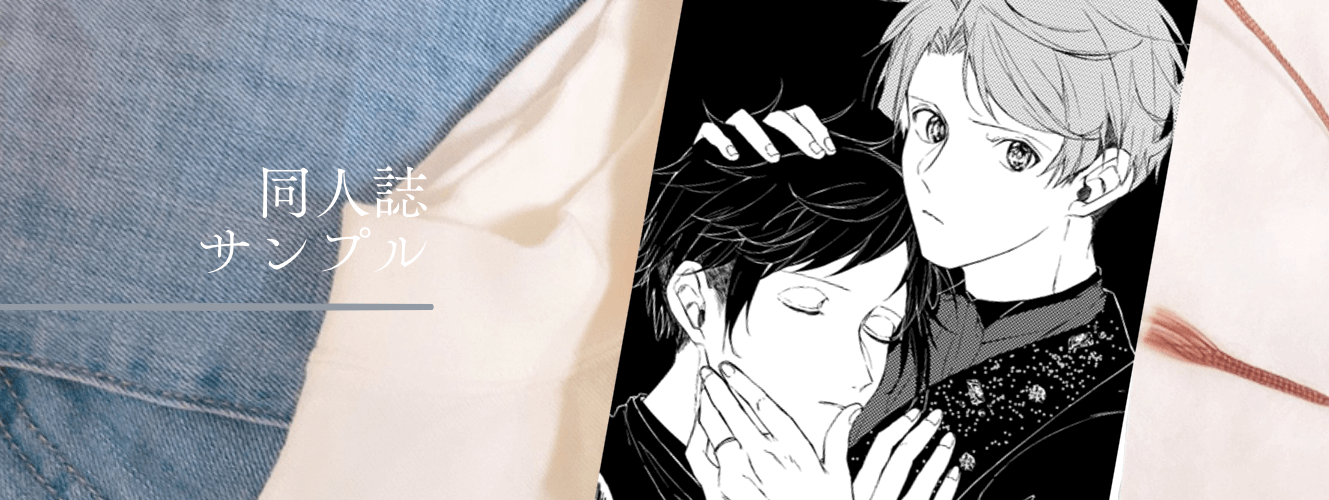
1.
すみません。止められなくて。
楽屋でまで頭を下げたマネージャーに、いいよこんなん勘違いだから、昨日から謝りすぎだって、もう、と笑ってみせた。
嘘なんて性に合わないくせに、ミツは笑って、俺たちの関係を隠す。 演技が本領、ってことになっているくせに、巧みに嘘をつくミツを見ていられないのは、俺の方だった。
二度とこんなことさせません、と、マネージャーは肩を震わせて、目にいっぱい涙を貯めて怒った。
俺たちの事務所が小さいことも、この小さな手にはどうしようもないことが簡単に起きてしまうことも、俺たちはよく分かっている。
「いいよ。俺たちは平気だから」
「そうだよ。マネージャー、ちゃんと寝てるか? オレらのことでファンの対応が大変だって、万理さんももう五日車で寝てるって聞いた……」
「私はいいんです。三月さんと大和さんを、守れなかった……」
ぐるん、と顔を背けて、こぼれそうになった涙を必死に隠す彼女に、ミツがスマホの画面を見せる。顔は見ず、さりげない仕草で。
「これさあ、昨日壮五が作ったんだけど、すっげえ辛くて。食ってる間、もう涙止まんねえんだよ。こなくそー! って気持ちになる。今日、昼休み、食べに来る?」
いきばす。行きます、と言おうとしたのだろう、泣き濡れて張り詰めた声が愛しくて、俺もミツも、マネージャーの背中にとんと手を置いた。小さな肩が、俺たちのためにこわばって、震えている。
俺たちを愛している彼女が、誰よりも必死に戦ってくれることを、目に焼き付けておこうと思った。
「オレたちはなんともないからさ」
たぶんマネージャーは気づいているだろう。俺とミツの関係をあばくその記事に、嘘なんてひとつもないことを。
それでも、俺たちは罪を重ねた。俺とミツの築いたささやかな、愛に満ちた世界を壊す嘘。
守るために壊す。
壊すために入ってきた世界で、守りたいものを見つけて、壊すのをやめた手で。守りたかったものを、壊す。運命なんてそんなものなのか。はじめに決めてしまったことは、形を変えて、かならず成される……タイムリープ映画の定石を思い出しながら、目じりを下げた。
「そうそう。ごめんな、こんなデタラメな記事のせいで、寝かしてやれなくて」
「オレたちは大丈夫だよ。お兄ちゃんを信じな」
ミツがにっこりと笑って、マネージャーの手にハンカチを握らせた。マネージャーが眉を下げて困ったような表情を見せる。くしゃりと頼もしく笑いかけるミツに、マネージャーの大きな目から、ぼろぼろと涙がこぼれた。
「ごめんな、泣かせて」
「三月さんは悪くないです……大和さんだって……」
おふたりを守れなくて、悔しいです。マネージャーの呟きに、ミツの大きな瞳が曇る。深い悲しみを引き受けて潤む瞳を見ていられずに、マネージャーの頭をぽんぽんと撫でた。
「そんなことより、ファンの子たち不安にさせてんの、早く何とかしないとでしょ。なんか大きい仕事取ってきてくれる?」
「あ……」
「マネージャーの営業手腕、信頼してるんで。よろしくな」
「はいっ!」
気合いたっぷりの返事に、手を離す。あとは任せるとミツに目配せして、楽屋を出る。
別れると言っても、ミツとの信頼が揺るぐわけじゃない。ただ、これまで当たり前にしてきた触れ合いがなくなって、数年前に戻るだけ。お互いのやりたいことも得意なこともわかっている分、俺たちは、昔よりずっと上手くやれるだろう。
夜まで仕事をこなして、事務所のスタッフに守られながら、タクシーを捕まえてもらって。あっ、という顔をした運転手に眉を下げ、帽子を深く被って寝たふりをする。上手くやっている。
重たい寮の玄関ドアを静かに開けると、リビングから明かりが漏れていた。
──七瀬さんのせいではありませんが…昔六弥さんと撮られた時のようにはいかないでしょうね。
──なんで?
──兄さんと二階堂さんは、巧妙に隠していましたけど、巧妙すぎたんです。一切の遊びの影がなかった清廉な二人が影で交際していたら、暴きたくなるものでしょ。
──どういうこと? 三月だって大和さんだって、悪いことしてないのに。
──兄さんは、バラエティはもちろん朝の情報番組にも出演が増えて、幼い子供から老人までが支持する、いわば「いい人」の代表です。二階堂さんも、映画やドラマの出演で、個性的な魅力を国際的にも評価されている。日本の芸能界の顔の一つです。ネームバリューがあるということは、二人とも、叩いた分だけ金になる。
──そんな言い方……三月は一織の兄さんだろ。
──だからですよ。私の兄さんを、こんなふうに食い物にする奴らを、野放図にさせている自分が……。
ぺたりぺたりと裸足でリビングに向かい、子どもらの密かな会話が聞こえなかった振りをして、いつもの力の抜けたお兄さんの顔を繕う。
さすが、イチは現実が良く見えてる。現実って言葉を辞書で引く前にイチの顔を見た方が意味がよくわかるだろう。……いや、顔は非現実的なくらい綺麗なんだけど。
「ただいまー。腹減ったわ。晩飯今から作んの?」
「あっ、おっ、おか、おかえりなさっ、いっ!?」
リクが慌てた様子でテレビを切り、そのままソファにつまずいて転びそうになる。溜息をつきながら、イチがリクのリモコンをうばい、背中に隠した。
「七瀬さん、危ないので座っていてください。おかえりなさい」
「ばば晩御飯、今日は一織が作ってくれます!」
「へえ、イチの飯か。和泉家の味じゃん」
「兄さんの仕事が長引く分、今日は逢坂さんが作ると聞いて、黙って見ては居られなかったので。大事なメンバーを傷つけさせるわけにはいきませんから」
何年経っても、誤魔化しの下手なところは変わらない。挙動不審なリクにも、やけに口数の多いイチにも気付かないふりをして、マフラーを解く。
仕事が長引くなんてのも、ミツが適当についた嘘だとわかっている。囲まれてすぐに帰れない、と言えず、仕事だとうそをついた……そんなところか。
俺よりもミツの方が風当たりは強いだろう。イチの言う通り、人に好感を抱かせやすいミツの容姿や態度は、アイドルのくくりを超えて、あらゆるバラエティで重宝されてきた。
「昨日の激辛麻婆豆腐もうまかったけど、まあ殺人的なうまさだったからな……イチなら安心だわ。お兄さん、ビールに合うやつがいいな」
「ほどほどに」
上着を脱ぎながら、眉を下げた。マネージャーにも、タクシーの運転手にも向けた表情は、いま引き出しの一番出しやすいところに入れてある。ちょっと眉頭に力を込めて、困った顔に出来れば、心優しい相手ほど突っ込んでこなくなる。
自分をさらけ出してでも守りたいと思っていたメンバーに、自分だけを守るための顔を向けるなんて、もうしたくなかったのに。
「お前さんたちにも苦労させてるな」
「何の話ですか。七瀬さん、しょんぼりした顔しないで。夕食、あなたの好きなオムライスですから」
「イチは好きな子に優しいなあ。お兄さんも甘やかされたい」
「やかましいですよ。たまたま冷蔵庫の材料がオムライス向きだっただけです」
イチはいつも通りだ。
ソウやイチは否定を貫いた。ナギも、意外にもタマまでもが上手く立ち回った。リクが何かを話そうとする度に、誰かがマイクの前に割って入る。
──兄さんと二階堂さんが交際なんて、しているわけがないでしょう。あの人たち、昔から私たち抜きで年下メンバーの今後について話すの好きでしたから、それでつい飲みすぎて酔いつぶれて、休むところがそういう施設しか無かったんじゃないですか? 。
──彼らの関係が友人以上に見えたことはありませんでした。大和さんも三月さんも、いつも僕らを支えてくれている、頼もしい二人です。
──ワタシも彼らを愛し、彼らもメンバーを愛しています。彼らがワタシに注ぐ愛情に、無粋な憶測で報いたいとは思いません。
──ヤマさんもみっきーも、こういう兄貴とか、とーちゃんがいたらいいのにって思うし、好きだし……なんも悪いことする人達じゃねーの、知ってるだろ。
それらのコメントの多くは報道には乗らない。必要なところだけを切り出して、『そういう施設しかなかった』だの、『無粋』だの、苦い表情で語られる部分だけが、美味そうに味つけられてネット上へ放り出される。
いくつもの言葉が、俺たちの周りを取り巻いた。
「じゃあ、俺は部屋で台本読みしてるから。晩飯できたら呼んでよ」
「はい!」
リクが妙にハキハキとした声で応じたのに、軽く眉を下げる。イチの目を見ることはできず、廊下に出た。責めもいたわりもしてほしくなかった。イチはどちらもしないだろうけど、だからこそ、答えを知るのが怖かった。
「……廊下、寒いな……」
ペタペタとスリッパを鳴らして、部屋に向かう。廊下の電気は煌々と点いているのに、やけに薄暗く感じた。
部屋に戻って、床に置いたテレビをつける。限りなく音量を絞って、他の誰にも聞こえないように、こっそりと芸能ニュースの録画を再生した。
3日経ってなお熱は醒めないらしい、俺とミツがライブで笑い合う写真が、敵将の首のように晒され、なじられている。いくつものSNSの書き込みが、次々に俺たちの笑顔に重ねられた。
『裏切り』『他のメンバーが可哀想』『ファンの感情を弄んだ』『グループのフレッシュなイメージがガタ落ち』『寮生活でも何をやっているか分からない』『彼らが共演者に優しかったのは寮で発散出来ていたから』『同性愛者の皆さんに勇気を与える行為』……。俺たちの大切なものが値段をつけて陳列され、好き勝手に値下げのラベルを貼られていく。そんなつもりじゃないなんて弁明は、意味をなさない。
映像が切り替わり、マイクを突きつけられて柔和に微笑む三人組が映った。
「アイドルの熱愛疑惑といえば十さん以来ですね!その後どうですか?」
「俺の恋人はずっとファンのみんなです。TRIGGERとして踊る俺を求めてくれる人がいる限り」
十さん、うまくインタビュー避けてるな……。
「二階堂さんと和泉三月さんとは、九条さんも個人的にも交流されていますよね!」
「二階堂大和さんとは二人での仕事も多く、役者として学ぶところもあります。JIMAやブラックオアホワイトを競ったライバルグループのリーダーとして申し分ありません。和泉三月さんの生き方は、ボクにはできない仕事です。同じプロとして嫉妬を覚えることもありますよ」
九条はさすがだよ、これ以上の質問を許さない雰囲気がある。
「抱かれたい男は、アイドルの恋愛についてどう思いますか?」
「俺たちを好きだと思ってくれてる奴に、後悔はさせない。夢中にさせてやる。俺たちはそうやって生きてきたし、生きていく。これからもずっとな」
こういう、いつだって自分を主語にして話せる強さに、助けられるんだよな……。
そして映像が、赤髪の少年に切り替わる。せつなげに眉をひそめて、こちらになにか求めるように、瞳をうるませてしょげた表情。
少年と呼ぶには月日も経ったのに、いまでもまだ、出会った頃と変わらないあどけなさを感じてしまうのは、俺ばかりではないだろう。
「オレは、こういう状況が続くことが、一番、大和さんや三月のファンの人にとってつらいと思うんです。大和さんも三月も、悪いことなんてしてないのに……だから、オレは、早くみんなの前でライブしたいなって思ってます」
「ライブですか?」
「はい! 笑って欲しいから、笑っていたいんです」
チャンネルの矢印を操作して、吸い込まれそうな、潤んだ瞳を記憶の向こうへ押しやる。今ミツが出演している、生放送のバラエティが映った。おそらく、さっきのリクたちは、これを見ていたんだろう。
ふっくらと優しげな恰幅に、ぎらついた大きな目をのせた芸人が、ひな壇から司会席のミツへ笑いかける。
「俺、三月くんならアリやわ。おしりとか柔らかそうやし顔かわいいし」
ミツは当たり前みたいに、笑顔でその言葉を受け止めている。悪意に満ちた空気、靄がかってすら感じる画面の中で、ひときわ明るく、はっきりと見えるのは、やっぱり、ミツだけだった。
いちばん眩しく見える相手に。
俺が、こんな思いをさせている。
「えー、オレ尻で割り箸割れるくらい尻硬いですよ! でも顔はいいです! アイドルなんで!」
「自分で言うやん! メンバーが惚れるくらいやもんなあ」
「まあ一織はオレの顔かなり好きですね。あいつオレの成人式の写真まだスマホに入れてるんですよ。成人式といえば……」
画面の中のミツが声を失う。俺の隣に伸びてきた手が、リモコンの消音ボタンを押していた。声もなく、ミツが笑って、フリップをさす。
「見てるんじゃないですか。番組」
「たまたまつけたらやってただけだって」
ミツの笑顔は、いつも通りに楽しげに、テレビの中の共演者たちに向けられている。俺に向くことの無い表情。今も、心ない言葉を浴びているのかもしれないのに。
「なあ、和泉プロデューサー」
いつだかと同じ呼び掛けに、すらりと立つ美しい男が、目を細める。
「もうその質問は通用しませんよ。追い出して欲しくないんでしょう?」
「……浮かない顔させてるな、お前さんにも」
「そうですね、宣伝効果も特に期待できそうにないので。ファンにとっても、私たちにとっても、マイナスの効果の方が大きすぎます。ファンやメンバーが疲弊する状況を変えるような話題は、マネージャーとも検討していますが」
イチの白く伸びやかな指が、テレビの電源を落とす。画面の向こうのミツの笑顔は、黒い箱の中に、永久に失われた。
「あなたのせいだなんて思わないでくださいね。二階堂さんと兄さんが何をしていようと、私はIDOLiSH7によりよい未来を考えるだけです」
「未来ね」
「浮かない顔に見えるとすれば、あなたと兄さんの覚悟に応えられない、私が不甲斐ないからですよ」
どう応じていいかわからず、首をかく。イチはすらりと背筋を伸ばしたままで、リモコンを差し出してきた。
「世話の焼ける、大切な兄たちなので」
イチの手からリモコンを受け取る。もうテレビをつけようとは思えなかった。電源を落とすと、イチのほおが、少しだけ満足げにゆるんだ。
「あなた達とはずっと助け合ってきたつもりです。助けられたことだってあります。……誰にも傷つけさせないし、奪わせないつもりです」
「はは……あんま気張るなよ」
「あなたがね。私はプロデューサーらしいので、こういう時が出番でしょう。あなたは当事者らしく、気を抜いて、いつも通りにしていてください」
「はいはい、仰せのままに。プロデューサー」
やれやれと肩を竦めて見せると、イチは少しだけ不安そうに眉を寄せ、踵を返した。ドアが閉まる音を椅子の背もたれ越しに聞いて、瞑目する。
眩しい。イチの理想も、フラッシュも、部屋の照明すら。
全部煩わしい。
ずっと、時間の止まった黒い箱の中で、蹲っていたい。
「いつも通りに……リーダーやれって……」
呟きに、ため息が混ざる。
イチ。俺は、IDOLiSH7の一番前で、泥を被るつもりだって言ったけど。
お前たちまで俺の泥で汚すつもりじゃなかったんだよ。こうなるのがいちばん怖かった。
俺たちの関係を、泥と思わなきゃいけないことも。あの眩しい男を、こんな暗がりまで引きずり下ろして、踏ん張らせていることも。
……俺のせいなのかな。
瞼を閉じてすら滲みてくる光が、瞼の血管をあかあかと透かし出すようで、眼鏡を外す。手のひらで目を覆うと、思ったよりも顔が冷えていた。
「明日も仕事か……」
明日の仕事は、雑誌やら番宣やら、演技に関係の無い仕事ばかりだ。できれば、演技の仕事が欲しい。
二階堂大和が感じる息苦しさもやるせなさも、役のつもりになってしまえば、遠くに押しやれる。今日はどの役を借りようか。なるべく何も考えずに済む、効率重視の、夜はちゃんと眠る男がいい。あの男はどうだろう、殺される教師役。初めてカメラの前で演じた、生徒のために苦しむ感傷的な男。あの男の、あの瞬間途切れた命を借りればいい──。
部屋の電気はついたまま。
そのまま眠りに落ちるのに、数分とかからなかった。
*




