方舟Ⅰ _暴かれて終わったオレたちの関係について
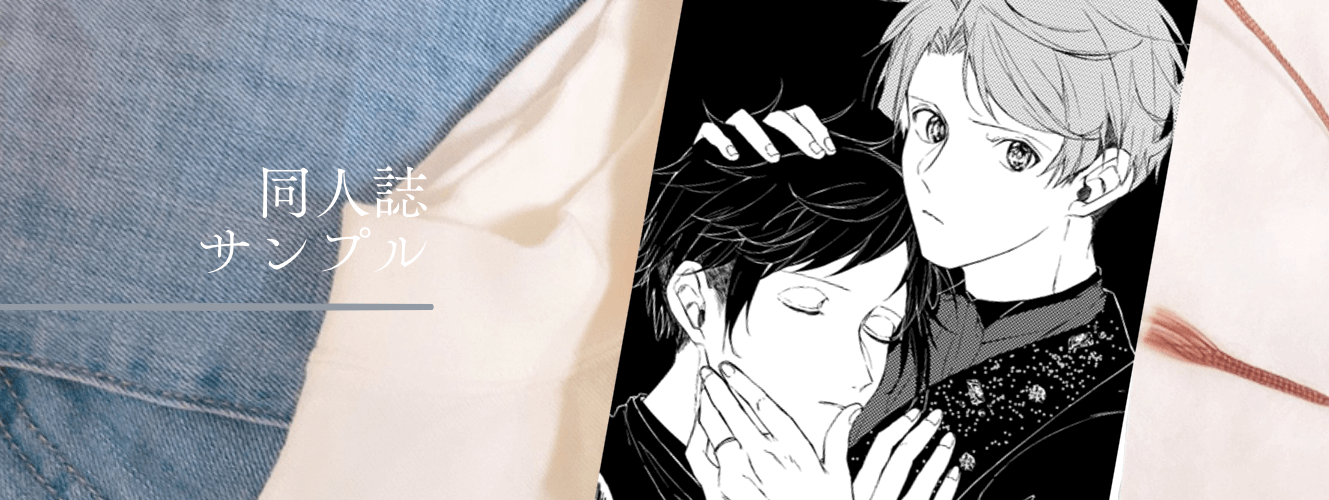
(中略)
カット、の声は鋭い。映画館の座席にぼんやりと明かりが戻るように、じっくりと日常へ帰っていく。白いシーツの上で、さっきまで別の男だった肉体に、二階堂大和が戻ってくる。同性愛者の俳優は、かすかなわびしさを残して、俺の裏側へ引っ込んだ。
きつく作った握りこぶしを解いて、血がめぐり始める時に似ている。指先が、じわりと痺れて熱くなる。手のひらの冷たさを隠すように、衣装の白いタックパンツのポケットに手を押し込んだ。
「お疲れ。いい、演技だった」
所謂「相手役」の男が、一緒になってベッドを降りる。人の良さそうな笑顔の向こうには、けれど、人の悪そうな薄暗い気配が透けて見えた。……そうあって欲しいと、俺が願っているだけかもしれない。俺に近づいてくる誰かが、俺を罰して欲しいと。
いい演技、じゃなく、いい、演技。含みのある言い方に、微笑を浮かべるのが一拍遅れた。
「やっぱ、もうちょっと欲しいですか」
「監督はいいと言ったから、きっと、今の君の演技は、求められている最大値なんだと思うよ。手加減なくね」
「……なんか、飲み物、持ってきますよ」
「ありがとう。僕も行くよ」
白いシャツははだけ、タックパンツの前も緩めて、下着がのぞく。寮でもしないだらしのない着崩しや、わざと下ろして乱した陰気な髪を崩さないよう、慎重に歩く。スタッフのひとりが、コーヒーをいれていたポットを持ち上げるのを見て、隣の男が声を上げた。
「あ、コーヒー、もしかして終わり?」
「萬作さん! お疲れ様です。いえ! 新しい熱いのを持ってきたので、ぬるいのは取り替えようかと」
「そうか、ならちょうど良かった。熱いのは苦手でね、2杯貰ってもいいかな」
「もちろんです! 今いれますね」
朝の十時、昨夜から働き詰めだろうスタッフは、微笑んでプラカップを手に取る。手際よく黒いホルダーに使い捨てカップを詰める手を向こうに、男が俺をちらりと振り向いた。
「聞いてるよ、猫舌だって。僕もなんだ」
聞いてる、というのが、一体誰からのことなのか。得体の知れなさを演出されたのか、本当にこういう人間なのか、これまで出会った役者の何人かに照らしても、この男がまだ掴めない。
クランクインから数日。もう数回、肌を重ねたあとのような演技をしていた。そのたびに、品定めするように俺を見ていた男。潮見萬作……何人もの大御所と縁の深い、舞台出身の俳優。当然、千葉志津雄や、Re:valeの千、何人もの知人と共演している。俺を誰からどう聞いて、どんな像を作り上げているのだろう。どう振る舞えば、こいつを満たしてやり過ごせる?
座ればシャツに皺がつく。衣装を崩さないためだと分かっているのだろう、塩見は、だらしなく生やしたすね毛を隠しもせず、コンクリートの壁にもたれた。
隣に空けてあるところに、肩を預ける。冷たくて硬い、セットの裏側の、石の壁。薄暗く、人の気配をへだてた場所に、自分を抱く役の男と、二人きり。
「僕との仕事じゃ、君を振り向かせられないんだな」
「そんなことないですよ。潮見さん、さすがだなって思います。勉強させていただいてます」
「そう? 君の肌に触れても冷たいし、濡れもしない。もっと預けて欲しいんだけどな」
「なんの感触もないよりマシですって」
「そうだね。そこにいるのにね」
何気ない会話の端々で、狡猾に、捕えようとする手が見える。軽い気持ちでぼろでも出せば、俺の本性を掴まれて、引きずり出されてしまいそうだ。カーテンの内側で、暴かれて奪われることに脅えてうずくまる、みじめでちっぽけで、けど誇り高くて愛情に飢えた、ささやかな幸せを願う俺自身が。
それでも不思議と、安らいだ。
腫れ物に触るように振る舞われるよりも、予想した通りの反応をしてくれる方が、よっぽど守りやすい。
ずっと、そうして生きてきた。忘れていた十何年を、体は覚えている。
「共演者なんだから、仲良くやりましょうよ。あんたも現場でいちいち煩わされたくないだろ? あんまりいじめられると、泣いちゃうかも」
「はは、そんな素振りも見せないくせに。泣いちゃえばいいのにね、つらいときくらい」
「泣いたって……いや、そしたら、あんたに泣かされたって言いふらそうかな。役柄的には、ぴったりじゃないですか? 俺が泣かされる側って」
「君が、君の心を塗りつぶした演技をするのが不思議なんだ」
話聞けよ、と毒づきそうになるのを、奥歯を噛んでこらえる。俺の唇の歪みで全て察したらしい、その男は、小さく含み笑いした。
「そのままの君ではダメなんだね。……なにか守っているのかな」
「……演技が、楽しいんですよ」
「そうだね。演技って、楽しいよね」
何を言っても、のらくらと、そうね、と返してくる男を思い出して、唇を内に巻き込んだ。食えないタイプだ。
演技は楽しい。これで認められてきた自負もある。この世界への背中を押してくれたやつらに、俺はうまくやれてるよなと振り向いて、さすがだよと笑いかけて欲しい……余計なことを思い出したことを、目の前の敵に見透かされた気配を感じ、目を閉じた。
……ただ、七人で。ただ、二人で。俺の望みは、いつも遠のいてしまう。
「楽しいことだから、楽しんでやりたいって、いつも思うのにね」
呟きは小さい。はっと息を飲んで、隣を見た。男は微笑んでいた。急に、あと二十年もしたら、ミツもこんな顔をするのかもしれないと思った。切なさを帯びた、けれどどこか満足げな、何かを掴んだ者の表情。
吐息して、男が続けた言葉に。やられた、と思った。
「僕に、彼と似たところはある?」
「……彼、って」
「僕に彼を見つけてくれないか」
やっぱり話を聞かず、男は続ける。そいつの中に用意された答えのとおりに、進まされている気がした。
けど、楽かもしれない。用意された道を歩くのは。最後にどこに行き着いたって、俺のせいじゃないから。
「ほんのひとかけらでいいよ。君を慰めたいわけじゃない。僕の演技で君を引きずり出せたら、気持ちいいと思ってね」
声をやわらげて、男は微笑む。おそろしいことなどなにも言っていないという顔で、男は、肩を鳴らした。
ふう、とまた吐息して、無害な中年の顔で。
「悪い顔は、得意なんだけど。君に好かれる顔を作ってみたい。演技のために」
男がコーヒーを啜る。
「悪役同士、仲良くやろう」
悪役。
言われてみると、悪い気はしなかった。
その方が楽かもしれない。いい奴の顔で悪いことをしていると言われるよりも、ずっと。
「……はは」
笑い声をコーヒーに溶かす。
唇をつけると、冷め始めたコーヒーが、喉の奥をすり抜けて、胃へと冷たく落ちていった。


