幼少期の写真にまつわるSS
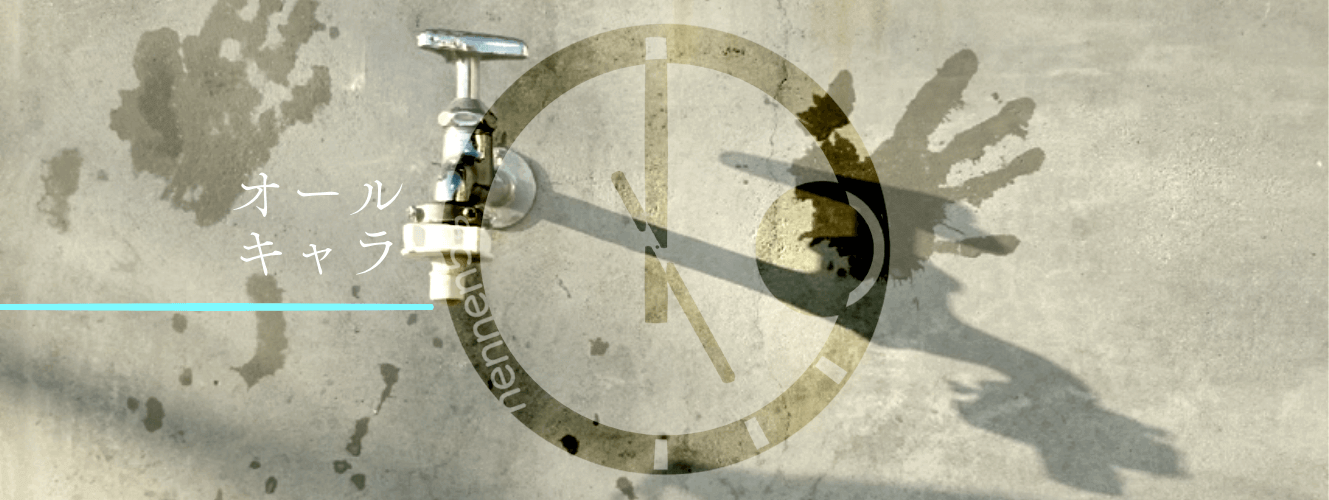
●一部の三月
「番組で使う写真ですか」
「うん。オレがちっちゃいころの写真。なるべく今と顔違うやつ! 誰のちっちゃいころでしょうかってやりたいんだよなー」
オフに時間ができるたび、実家を手伝いに帰ってくる三月に、父はショーケースのケーキを補充しながら首を傾げた。三月は、ピークの落ち着いたレジで、愛ドリッシュNightの企画のためにアルバムを広げている。三月の父は、唇に手を当てて、ふむ、と考え込んだ。
「一織も三月も、私と母さんの顔立ちに似ていると小さい頃からわかっていましたから。それほど大きな変化はないと思いますよ」
「父さんと母さんはそうかもしんないけど、オレらのことWeb番組でしか知らない人が、アーッてなるかもしんないからさ」
「そうなんですね。ちなみに父さんのおすすめはこれです」
三月の父は、レジの後ろに立ててあった店用の赤い手帳を開き、そこから一枚の写真を三月に手渡した。
「え? 何これ! オレ見たことないんだけど!」
「父さんの写真の腕に母さんが嫉妬するので、普段は隠すようにしています」
「あ、そう……えーこれかわいいなーオレ……オレが三歳くらいの時?」
「ええ。母さんのお腹にいる一織にキスがしたいからと、母さんに抱きついて離れない三月です」
「そんなことしたっけ? 弟が生まれるのが嬉しくて、ずっとくっつき回ってはいたけど」
きょとんと写真を矯めつ眇めつする三月に、三月の父は端正な顔立ちを緩めて、さらにもう一枚の写真を手帳から取り出した。
「それからこれは、そんな三月にキスする母さんです。美人ですよね」
「何でオレ今のろけられたの……? 若い頃の母さん、めっちゃ今のオレと似てんなー。さすがにこれは使えねえけど……」
「一織が生まれる頃、三月には寂しい思いをさせると分かっていたので、私も母さんも、三月の写真を沢山撮っていたんですよ」
「……まあ、弟が優先なのはしょうがないじゃん」
「でも、私も母さんも、一番も二番もなく、三月と一織を愛していますよ」
「分かったって! ほんとすぐそういうこと言う……あ、いらっしゃいませ!」
三月が、二枚のキスの写真を挟んで、レジの上のアルバムを閉じた。慣れた様子で一つ一つのケーキを客に勧める姿は、アイドルだというのに、洋菓子店で修行中の若者のようにしか見えない。
三月の、アイドルになるという夢には、目には見えない期限があった。誰も言葉にはしない、二十代という壁。二十歳を過ぎてもアイドルを目指すことは、特段歌やダンスに秀でるものがあるわけではない三月には、厳しい道だった。
昔から三月を知っている商店街の人々は、童顔とはいえ昔より大人びた三月を見て、フォンテショコラも将来安泰ね、立派な長男、と三月を褒めた。そのたび三月は、オレはアイドルになりたいんで、と笑っていた。その笑顔を、その夢が、この店が曇らせてしまわないように、と、父は願い続けていた。
「三月」
「うん? 何?」
初老の女性客は、三月がアイドルだとは気付かないまま店を去った。インターネットを中心に露出を増やしているIDOLiSH7は、まだインターネットに馴染みのない層には、顔が知られていない。
声をかけた父に、三月は以前と同じ大きな瞳で振り向いた。
「この写真もいいと思います。父さんが一番好きな三月の写真です。残念ながら、撮ったのは父さんではないですが」
父の手の中には、スマートフォンがあった。覗き込んで、三月が破顔する。
「オレも一番好き! けど、探してんのは小さいころの写真なんだって」
「探すの、手伝いますよ」
「うん」
三月の父のスマホに表示されたのは、IDOLiSH7の公式サイト。七人で並んでこちらに笑いかける、アイドルの和泉三月の笑顔があった。
「また、メンバーの方といらしてくださいね」
「うん! あいつら甘いの好きだから、喜ぶよ。オレがオフだと残り物のケーキが食えるからって朝から目きらきらさせてんだぜ。辛党のやつもいるから、あいつには別になんか買ってってやんなきゃな……」



