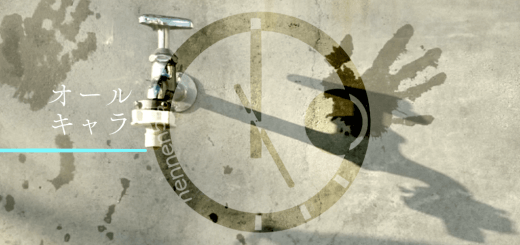めぐる

今日の三月くんしんどそうだったから、謝っといてよって言われたんだけど、伝えてもらえないかな。
何人もの口を伝って俺のところに舞い込んだのは、高いところが苦手なミツに吊り橋ロケを依頼したディレクターの謝罪。直接言えよ、と思うものの、それ以上に、あいつはまた頑張っちゃって、とやりきれない気持ちが勝った。
そんなに頑張んなくたっていいよ。誰が止めても、あいつは頑張り続けるんだろう。それしかしてこなかった、そうしないと誰も認めてくれない、そんな焦りさえ感じ取れるほど。
両親が仕事で出かけてばっかりの家の長男って、そういうもんなのかね。
「ただいまー」
呟きながら三和土を見下ろせば、身長の割には大きい、靴紐のぐちゃぐちゃに結ばれた靴が一足。靴紐はきつく二重に結んであって、解けそうにない。靴底や側面は真新しい泥で汚れていた。
この靴で、高所ロケに行ったんだろう。靴が脱げてしまわないように、万が一にも下を見なくていいように、きつく、固く靴紐を結んで、そんなのおくびにも出さずに意地を張って笑って。
……ほんと、高所恐怖症の奴にさせるロケかよ。色味の乏しい、奥地の林で吊り橋ロケ。元気なイメージのアイドルでもビビらせて面白い絵面にしたい気持ちはわかるけど。デビューしたての俺らを引き立ててやろうって気持ちだったのかもしんないけどさ……。
天気も少し悪かった、山奥に吹き荒れる風を想像して、あの靴にこびりついた泥を思い返せば、口の中までじゃりじゃりしてくる。
さっさと、謝ってたぞーって言ってやるか。
リビングを覗くと、キッチンの明かりだけがついていた。
「おーい。ただいま」
薄暗いソファに鞄を下ろしつつ、キッチンに立つオレンジ頭に声をかける。おー、と返ってきた声は予想外に小さくしょぼくれて聞こえて、どきりとした。俯いて、火のついていない鍋を見つめて、ミツは物思いにふけっている。
一人の殻に閉じこもって、誰にも触れられたくないと自分の身を抱いて。誰に声をかけられても鬱陶しいのに、声をかけてこないやつはムカつく。俺の機嫌をうかがってくるやつも、俺を気にしないやつもムカつく。闇雲に壊して壊されたいような、やり場のない不快感が、身体中を這いずり回る。
その感情に、覚えがあった。……これ、謝ってたぞって言われたって、収まんないやつだな。
曇った表情が痛ましくて、目をそらす。
汚した靴下を脱いだままなのだろう、スリッパに突っ込まれた裸足は、夏だというのに冷たそうに白い。ミツに元気がないだけで、俺まで肌寒く感じるから不思議だ。
こんなにわかりやすく落ち込んでいるミツを見るのは初めてかもしれない。いつもならぴょこぴょこと跳ねる髪まで萎れて見える。
励ましてやりたい。俺が、ミツを笑わせることができたら。
どうしてやったらいいのかわからないまま、手を上げる。
「なんかあった?」
キッチンに足を踏み入れても、ミツはこちらを見なかった。
とりあえず、俺の方、向かせてみるか……。
「お兄さんに話してみろよ」
ぽん、と軽く頭に載せた手を逃れるように、ミツが体をのめらせる。その手から菜箸が落ちて、俺のスキニーの裾に煮物の汁が飛んだ。
「あ……」
あ、失敗した。多分ミツは気づいた。俺の、慰めようと伺う表情に。
一瞬だった。戸惑いのかたちに歪んでいた眉が、ぱっと吊り上がり、目は楽しげに弧を描いた。
不出来を咎められた子供のような頼りない顔が、作り笑いの顔になるまでのほんの一瞬が、胸をついた。
「あー、ごめん!大丈夫だったか?熱くはないと思うけど……」
ミツが屈んで箸を拾い、汚れた俺の裾をあらためる。
「大丈夫。後で洗うから。ミツは?ミツこそどうなんだよ」
唇を舐めて訊ねると、ミツは俺のズボンの裾をぽんぽんとはたいて、立ち上がりざまに俺の脇をすり抜けていった。
「オレ?大丈夫大丈夫!つーか何の話だよ、はは」
かしゃん、かしゃん。流しに菜箸が落とされる軽い衝突音が反響する。
自己評価が低くて、プライドの高いやつ。その、触れられたくない一線を越えてしまった。
励ましたかったのに、傷つけた。
ミツの表情は前髪に隠れて見えない。ミツはさっとエプロンの紐を外して、頭を下げてエプロンを脱いだ。
「腹減ったなー、オレ外で食ってくる。大和さん、出前でも取ったら」
「え、ミツ、これ……」
「肉じゃが。あいつら帰ってきたら、適当に食べといて。行ってきます」
「っておい、あんな泥靴でどこ行く気だよ!」
「うるさいな、どこでも行けるっての!」
思わずあげた大声に、さらに大声が返ってきて、怯んだ隙にミツの背中が遠くなる。あっという間に、ミツは靴を履いて玄関を出ていってしまった。
「あっ……スマホ……」
ふと見れば、リビングのテーブルにミツのスマホが置きっぱなしになっている。画面の硝子はバキバキにひび割れ、置き去りにされていても、誰かからの連絡のいくつもの通知を光らせていた。ミツを頼って、ミツをかわいがる、誰かからの。
この分じゃ、財布も持っていないだろう。
お前さん、ちゃんと人に頼れてるか。そう聞きたかったのは、俺があいつに頼られたいからかもしれない。
俺のエゴだ。頑張ってる奴の頑張りに乗っかって、自分の存在意義を確かめようとした。ミツに頼られて、しっかり者のリーダーでいたかった。……のかも、しれない。ミツを励ましたい、純粋なそいつを救ってやりたいなんてきれいな気持ちが、不純な俺に起こるのなんて、きっとそういう理由しかない。
鍋に手をかざすと、もうかなり冷めていた。味も馴染んでいるだろう、おたまを持ってきて、人参としらたきと肉と玉ねぎと……程よい大きさに切り分けられた具材をすくう。若い食べ盛りたちに見つかる前に、自分の分を取り分ける。箸を出して、立ったまま小鉢のじゃがいもを摘んだ。
「うま……」
ほろりと、肉じゃがの新じゃがが口の中で崩れた。
「あー、ミスった……こっちでよかったな」
メシ作ってくれてありがとう、ロケお疲れさん。高いところなんか行って、気圧差で身長縮まなかったか?
今更、かけるべきだった言葉がいくつも思い浮かんで、頭の中を巡る。具材をすくうにはおたまが必要で、それを食べるには箸がいい、ひとつ間違えればうまくいかずに崩れてしまうことなんて、ずっと分かっていたはずなのに。
ほっとする醤油とだしの味つけに、ぐっと胸が詰まった。
落ち込んでる時にまで、こんなにうまいメシ作ってさ。
「良い奴って、バカなんだな」
ほっくりと煮込まれた芋と、初めの頃はめったに食卓に上がらなかった牛肉を、一緒くたに箸にとる。
何事もなかったみたいに、みんなでこれを囲みたかったんだろうに。
肉とじゃがいもを口に突っ込む。少し冷めて食べやすくなった肉じゃがは、やっぱり美味しかった。
財布も持たずに飯を食いに行ったミツの分も、ラップをして取り分けておいてやろう。冷めたってちゃんと美味いから。
「ごめんな」
伝えられなかった謝罪は、もう誰かの言葉ではない、俺の言葉になっていた。